技術・人文知識・国際業務の資格概要

① 在留資格の趣旨
【技術・人文知識・国際業務とは】
この在留資格は、特定の専門的な知識や技術を活かした職務に従事するための在留資格です。この資格は、日本の企業や団体が専門知識を持つ外国人を雇用することを目的としており、 大きく以下のとおり分類されます。
- 理工学系の知識を活かす「技術分野」
- 法律や経済、社会科学など人文系の知識を用いる「人文知識分野」
- 通訳や翻訳、海外取引などの国際的な業務に従事する「国際業務分野」
日本の国際競争力を高めるため、こうした分野で外国人の力を活用することが期待されています。「技術・人文知識・国際業務」は、通称「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれることから、この記事では「技人国ビザ」という用語で説明します。
【従事できる職業】
技人国ビザでは、外国人がこれまで学んできた知識、仕事で培ってきた経験、または母国の文化や言語に関する知識と関連性のある業務であれば従事できます。入管法上では「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学分野、人文科学分野、または外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする分野での活動」とされています。該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者などがあげられます。
【該当しない職業】
専門知識を必要としない業務や、外国人本人の学歴・職歴や文化などと関連しない業務は、技人国ビザの資格要件には該当しません。また公私の機関との契約に基づいていない場合も基準に該当しません。さらに特定技能や技能実習がが対象とするような単純労働も、技人国ビザの資格要件からは外れます。
【行政書士への相談と依頼した場合の相場】
技人国ビザを得るためにはいくつかの条件があります。職務内容と大学/専門学校の専攻との関連性、経歴要件、実務経験、有効な雇用契約、勤務する会社の安定継続性などを証明するための提出書類を準備なければなりません。入念な事前準備により、自分たちで許可を得るこことももちろん可能ですが、多くの時間を費やします。費用がかかるというデメリットはありますが、専門家である行政書士に依頼するのもひとつの方法です。料金の相場は、認定証明書交付申請・変更許可申請で6万円〜20万円となっています。
② 技人国ビザの要件
【学歴または実務経験】
●技術分野(理系職)
- 大学や専門学校における理系学部の卒業、または10年以上の実務経験が必要です。
- 対象職種例:ITエンジニア、機械設計、システム開発など
●人文知識分野(文系職)
- 大学/専門学校卒業、または10年以上の実務経験
- 対象職種例:経理、マーケティング、法務、貿易業務など
●国際業務分野
- 3年以上の実務経験(通訳・翻訳・語学指導など)。ただし大学で専攻していれば経験は不要です。
- 対象職種例:翻訳・通訳、海外営業、外国語教師
【勤務先企業/事業主と申請者の間に有効な雇用契約があること】
●契約形態
正社員・契約社員・派遣社員でも可(アルバイト・パートは不可)
●給与
日本人と同等以上であること(最低20万円程度が目安)
●待遇
日本人と同等以上の待遇(最低でも月給20万円程度が目安)
【勤務先企業/事業主に事業の継続性/安定性があること】
●事業の実態
登記事項/事務所証明書類/業務証明書類により証明
●財務状況
健全であること
●売上/取引
安定していること
●社会保険・労働保険
適切に加入していること
●外国人雇用
必要性が証明できること
必要書類・審査期間

③ 必要書類(在留資格変更許可申請の例)
【所属機関カテゴリーとは】
所属する企業の規模により提出書類が異なります。区分は以下のとおりです。
●カテゴリー1
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人,認可法人
- 日本の国,地方公共団体の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- イノベーション創出企業
- 一定の条件を満たす企業等
●カテゴリー2
- カテゴリー1以外で源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上団体/個人
- 「在留申請オンラインシステム」の利用申出の承認を受けている機関
●カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体/個人
●カテゴリー4
カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体/個人
【共通書類】
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
- パスポートと在留カード (提示)
【カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書】
●カテゴリー1
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
- 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
- イノベーション創出企業であることを証明する補助金交付決定通知書の写しなど
- 「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する認定証等の写しなど
●カテゴリー2
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
- 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(カテゴリー3で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る。)
●カテゴリー3
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
【専門学校を卒業し専門士又は高度専門士の称号を付与された者】
- 専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書1通。
- 外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定学科の修了者は修了証明書1通
【派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)】
- 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする雇用契約書等 1通
【カテゴリー1・2以外の提出書類】
●申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- 労働契約を締結する場合:労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
- 日本法人である会社の役員に就任する場合:役員報酬を定める定款の写し、又は報酬を決議した株主総会の議事録。報酬委員会が設置されている会社は委員会の議事録)の写し1通
- 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合:地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
●申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
- 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
- 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
- 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。DOEACC資格の場合は、レベルAからCの認定証1通
- 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
- IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
- 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
●所属に関する書類
- 登記事項証明書 1通
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
- その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
- 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
【カテゴリー1・2・3以外の提出書類】
●源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合 →外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の資料 1通
- 上記を除く機関の場合 →給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(写し)、または納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
④ 必要書類(在留資格認定証明書交付の例)
【共通書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記し簡易書留分の郵便切手を貼付) 1通
【カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書】
●カテゴリー1
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
- 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
- イノベーション創出企業であることを証明する補助金交付決定通知書の写しなど
- 「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する認定証等の写しなど
●カテゴリー2
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
- 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(カテゴリー3で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る。)
●カテゴリー3
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
【専門学校を卒業し専門士又は高度専門士の称号を付与された者】
- 専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書1通。
- 外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定学科の修了者は修了証明書1通
【派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)】
- 派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
【カテゴリー1・2以外の提出書類】
●申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- 労働契約を締結する場合:労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
- 日本法人である会社の役員に就任する場合:役員報酬を定める定款の写し、又は報酬を決議した株主総会の議事録。報酬委員会が設置されている会社は委員会の議事録)の写し1通
- 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合:地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
●申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
- 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
- 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
- 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。DOEACC資格の場合は、レベルAからCの認定証1通
- 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
- IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
- 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
●所属に関する書類
- 登記事項証明書 1通
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
- その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
- 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
【カテゴリー1・2・3以外の提出書類】
●源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合 →外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の資料 1通
- 上記を除く機関の場合 →給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(写し)1通、または納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料1通
⑤審査期間
認定申請、変更申請の場合は1〜3ヶ月が目安ですが資料の追加提出などで1ヶ月以上遅れることもあるります。事前に書類をしっかり準備することで、審査期間を短縮できる可能性もあります。お急ぎの場合や手続きに不安のある方は、行政書士に相談するのもお勧めです。
不許可事例
⑥不許可事例
【学歴や職歴が要件を満たしていない】
事例① 情報技術者として申請したが、IT関連学位がなく実務経験も10年未満
事例② マーケティング職として申請したが、経営関連学位がなく実務経験も10年未満
- 理由:学歴や実務経験の要件を満たいていない
- 対策:情報系学部を卒業しているか、実務経験があるかどうかについて確認する。実務経験の場合は証明書を添付する。
【職務内容が「技人国」に該当しない】
事例① 「通訳」として申請したが、実際の業務が事務や接客を含んでいた
事例② 「エンジニア」として申請したが、単純なデータ入力業務が中心だった
- 理由:業務内容が「技術」「人文知識」「国際業務」のいずれにも該当しない
- 対策:職務内容を明確に記載し、「技人国」の要件に合致することを示す。雇用契約書や業務説明書を提出し、職務内容の適正さを証明する
【勤務先の事業の安定性・継続性が疑わしい】
事例① 設立直後の会社で売上実績がなく、申請したが不許可
事例② 会社が赤字続きで、直近の決算書が審査で問題視された
事例③ 代表者が過去にビザ関連のトラブル(偽装雇用など)を起こしていた
- 理由:経営状態が不安定な企業は、外国人雇用を継続できる保証がないと判断される。過去の違反歴がある企業は、審査が厳しくなる
- 対策:直近の決算書(できれば黒字)や納税証明書を提出し、事業の安定性を証明する。まだ売上実績が少ない場合、事業計画書を提出して今後の見通しを説明する
【日本人と同等以上の給与が支払われていない】
事例① 申請者の給与が月額15万円と低すぎたため不許可
事例② 日本人よりも低い賃金を提示していたため不許可
- 理由:「日本人と同等額以上の報酬」が条件(月20万円以上が目安)。外国人だから安く雇う、といったようなケースは不許可
- 対策:日本人と同等の給与水準(20万円以上推奨)を設定。雇用契約書に記載する給与額が適切か確認
【偽装雇用・不正申請】
事例① 実際には働かないのに「雇用契約書」を偽造して申請
事例② 「エンジニア」と偽って申請
- 理由:入管は厳格に審査を行い、不正が判明すれば即不許可。今後のビザ申請も厳しくなる
- 対策:正しい内容で申請する(嘘の職務内容での申請は厳禁)。入管が求める追加書類には誠実に対応する
まとめ
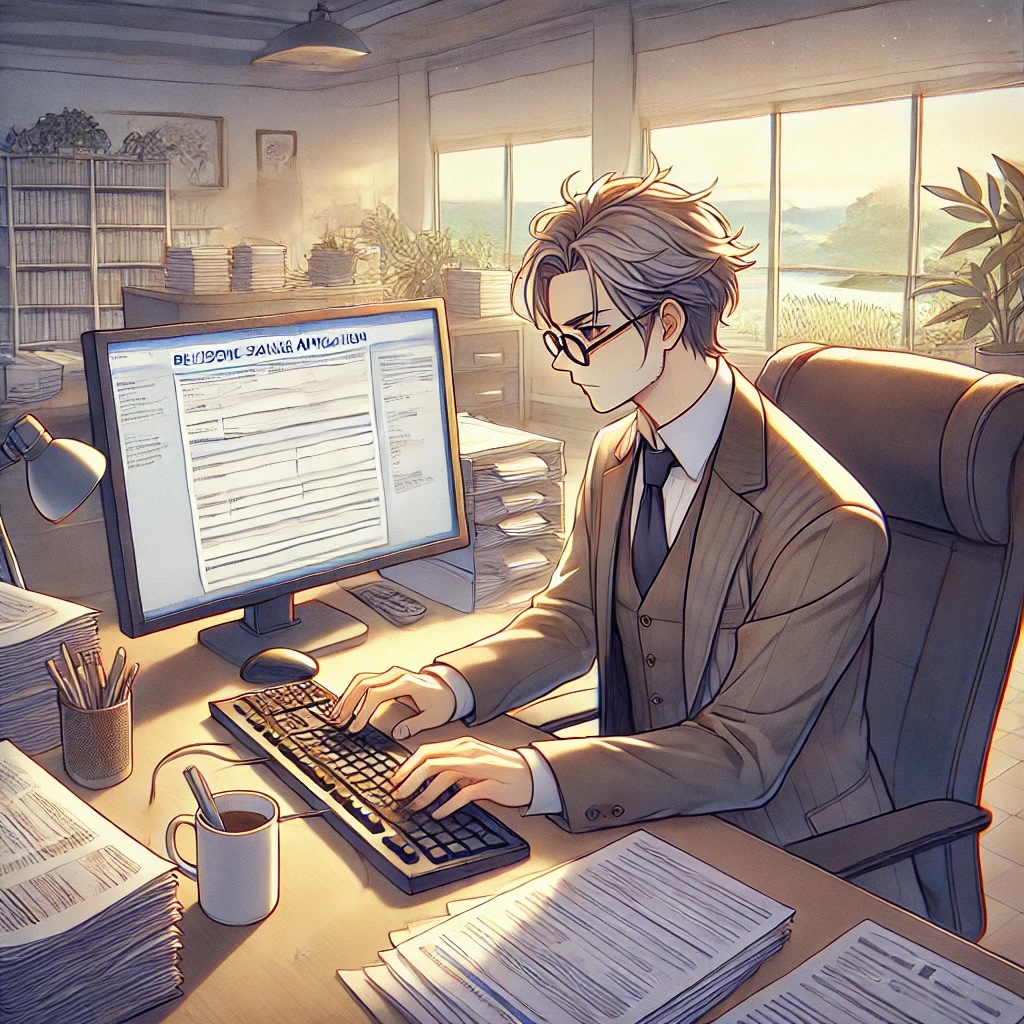
記事作成:浅野 長慈 (在留資格申請取次行政書士)
地方公共団体勤務の後、海外人材紹介会社、国内監理団体にて外国人材ビジネスを経験。2024年、アンコール事務所を開設。


