資格概要 -Overview-

① 資格の概要
「永住者」の在留資格とは、日本国内で長期間居住し、安定した生活基盤を持ち、社会に貢献している外国人に対して与えられる在留資格です。この資格を取得すると、日本での滞在に制限がなくなり、働ける職種や活動内容が自由になります。また、在留期間の更新手続きも不要となり、出入国管理局での手続きが大幅に簡略化されるという利点があります。日本での生活基盤がしっかりしている外国人が、長期にわたり日本社会に貢献し続けることを目的として設けられた資格です。世間では一般的に日本でのこの在留資格を「永住権」「永住資格」「永住ビザ」などと呼ばれることが多いためから、この記事では「永住ビザ」という用語で説明します。
【永住ビザのメリット】
永住ビザの取得条件は、他のビザとは異なり、滞在期間や日本国内での生活状況、そしてその外国人が社会にどれだけ貢献しているかが主な判断基準となります。これにより、日本での安定した生活と、将来的な社会的貢献が期待される外国人が永住を許可されます。永住ビザが許可された場合、次のようなメリットがあります。
- 在留期間の制限がなくなる:永住ビザを取得すると、期間更新の必要がなくなり、無期限で日本に滞在できます。通常の在留資格の更新手続きが不要になるため、手続きの負担が軽減されます。
- 活動の制限がなくなる:どのような職業にも就くことが可能となり(公務員その他一部の職業を除く)、転職や副業も自由に行うことができます。
- 社会的信用が高まる:永住ビザを持っていると、住宅ローンやクレジットカードの審査が通りやすくなるなど、金融面での信用が高まります。
- 家族の生活安定:永住者の配偶者や子供も、比較的簡単に在留資格を取得・維持しやすくなります。また、家族全体で日本での生活基盤を安定させることが可能です。
- 母国での権利は失わない:国籍の変更はないことから、母国にて付与されている権利を失うことはありません。また永住者は日本を一時的に離れる際、再入国許可を受ければ一定期間日本国外に滞在することも可能です。
- 社会保障制度へのアクセス:永住者は他の外国人と同様に、日本の社会保障制度(健康保険、年金など)を引き続き利用できますが、永住資格は長期的な生活を考慮する上で、制度利用の継続性に安心感を与えます。
- 経済的メリット:永住者になると、ビジネスや投資の自由度が増します。自営業や会社設立をする際にも、特別な制限を受けずに活動できます。
- 帰化申請の準備段階:永住者資格は、日本国籍を取得する「帰化」の要件を満たすためのステップとしても有用であると言えます。
【永住ビザ申請の留意事項】
永住ビザの取得には厳しい要件があるため、事前準備と計画が必要です。この在留資格を得るためには、クリアしなければならないいくつかの条件があり、誰でも許可されるものではありません。下記の資格要件について、様々な側面から厳しく審査を受けることとなります。また、要件をクリアしていることを証明するための提出書類は限りなく正確である必要があり、また量も膨大です。入念な事前準備を経て申請に臨む必要があります。自分たちで申請することももちろん可能ですが、申請書類を適切に作成することは、かなり難易度も高く多くの時間を費やします。費用がかかるというデメリットはありますが、専門家である行政書士に依頼するのもひとつの方法です。料金の相場は、10万円から30万円となっています。
② 資格要件
永住者の在留資格を取得するためには、以下の主な要件を満たす必要があります。
【素行善良要件】
- 法律遵守:日本の刑法や特別法に違反していないこと(過去の犯罪歴や交通違反なども含まれる)。
- 税金や保険料の支払い状況:所得税、市県民税、年金、健康保険料などを適切に支払っていること。
- 社会的な信用:日常生活においてトラブルを起こさず、近隣住民や職場で良好な人間関係を築いていること。
【独立生計要件】
- 安定した収入:申請者本人、もしくは配偶者や扶養者に、安定した収入や資産があること。年収の基準は家庭の人数などにより異なる。
- 安定した雇用状況:雇用契約が継続しており、職場環境が安定していること。
- 生活費の適切な支出:家計がバランスよく運営されていること(家計の赤字がないこと)。
特に、日本での長期間の滞在中に無職の期間が長かった場合や、借金がある場合には、注意が必要です。
【国益要件】
- 在留期間:原則として、引き続き10年以上日本に在留し、このうち5年以上は就労可能な在留資格(特定技能1号・技能実習を除く。)であること。日本人や永住者の配偶者である場合、婚姻期間が3年以上あり、かつ直近1年以上日本に居住していること。定住者ビザの方の場合、5年以上日本に居住していること。高度専門職のポイント制度に基づいている場合は1年に短縮される場合もある。
- 在留資格の適正性:現在の在留資格の活動を適正に行っていること。職業や地域活動などで、日本社会に貢献している場合は有利になることがある。
- 公共負担の回避:生活保護を受けていないこと。
- 国家安全保障:反社会的勢力やテロリズムに関与していないこと。
また申請者が今後も引き続き日本に定住し、生活する意思があることが必要です。さらに日本語能力も間接的に国益要件に影響を及ぼす場合があります。日本で生活する上で必要なレベルの日本語が使えることが求められる場合もあります。
必要書類・審査期間・交付される在留カードの期間

③現在お持ちのビザが就労系ビザの場合
【共通申請書類】
- 永住許可申請書
- 証明写真1葉(4cm×3cm)
- 在留カード/パスポート
- 永住許可を必要とする理由書
- 申請人を含む家族全員 の住民票
- 健康保険被保険者証の写し
- 身元保証書
- 身元保証書に係る資料(運転免許証、在留カードの写し等)
- 了解書
- 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみ)
(1) 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
(2) 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
(3) その他、各分野において貢献があることに関する資料
- 「在職証明書・確定申告書控えの写し・営業許可書の写し・職業に係る説明書及びその立証資料」のいずれかの書類
- 次のの5税目全ての情報が記載された納税証明書
①源泉所得税及び復興特別所得税
②申告所得税及び復興特別所得税
③消費税及び地方消費税
④相続税
⑤贈与税
- 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明するいずれかの資料
(1) 預貯金通帳の写し
(2) 不動産の登記事項証明書
(3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
【技術・人文・国際業務 などの方の申請書類】
- 住民税の課税(又は非課税)証明書 →直近5年分
- 住民税の納税証明書 →直近5年分
- 住民税を適正な時期に納めていることを証明する通帳の写し等(住民税が給与から天引きされていない方) →直近5年分
- ねんきん定期便又はネットの「各月の年金記録」の印刷画面 →直近2年分
- 国民年金保険料領収証書の写し(直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方) →直近2年分
- 国民健康保険料納付証明書(国民健康保険に加入している方) →直近2年分(直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は不要)
- 国民健康保険料領収証書の写し(国民健康保険に加入している方)→直近2年分(直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は不要)
- 健康保険/厚生年金保険 料領収書の写し直近2年分。または社会保険料納付証明書又は社会 保険料納入確認(申請)書直近2年分
【高度専門職又は特定活動の方の申請書類】
- 高度専門職ポイント計算表
- 高度専門職ポイント計算結果通知書の写し(80ポイント以上の方のみ)
- 高度専門職ポイント計算に 係る疎明資料
- 住民税の課税(又は非課税)証明書 →80ポイントの方は直近1年分・70ポイントの方は直近3年分
- 住民税の納税証明書 →80ポイントの方は直近1年分・70ポイントの方は直近3年分
- 住民税を適正な時期に納めていることを証明する通帳の写し等(住民税が給与から天引きされていない方) →80ポイントの方は直近1年分・70ポイントの方は直近3年分
- ねんきん定期便又はネットの「各月の年金記録」の印刷画面 →80ポイントの方は直近1年分・70ポイントの方は直近2年分
- 国民年金保険料領収証書の写し(直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方) →80ポイントの方は直近1年分・70ポイントの方は直近2年分
- 国民健康保険料納付証明書(国民健康保険に加入している方)(直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は不要) →80ポイントの方は直近1年分・70ポイントの方は直近2年分
- 国民健康保険料領収証書の写し(国民健康保険に加入している方)(直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は不要)→80ポイントの方は直近1年分・70ポイントの方は直近2年分
- 健康保険/厚生年金保険 料領収書の写し、または社会保険料納付証明書又は社会 保険料納入確認(申請)書 →80ポイントの方は直近1年分・70ポイントの方は直近2年分
※高度専門職又は特定活動以外(70ポイント以上保有)の日本人/永住者の配偶者等・定住者・就労ビザをお持ちの方は、行政書士などにお問い合わせください。
④現在お持ちのビザが身分系ビザの場合
【共通申請書類】
- 永住許可申請書
- 証明写真1葉(4cm×3cm)
- 在留カード/パスポート
- 申請人を含む家族全員 の住民票
- 健康保険被保険者証の写し
- 国民健康保険被保険者証の写し(国民健康保険に加入している方)
- 身元保証書(身元保証人様が作成します)
- 身元保証書に係る資料(運転免許証、在留カードの写し等)
- 了解書
- 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみ)
(1) 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
(2) 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
(3) その他、各分野において貢献があることに関する資料
- 「在職証明書・確定申告書控えの写し・営業許可書の写し・職業に係る説明書及びその立証資料」のいずれかの書類
- 次のの5税目全ての情報が記載された納税証明書
①源泉所得税及び復興特別所得税
②申告所得税及び復興特別所得税
③消費税及び地方消費税
④相続税
⑤贈与税
【身分系在留資格ごとの申請書類】
- 永住許可を必要とする理由書(定住者・家族滞在)
- 戸籍等関係書類
a. 配偶者の戸籍謄本(日本人の配偶者)
b.日本人親の戸籍謄本(日本人の実子)
c.配偶者との結婚/婚姻証明書等(永住者・特別永住者の配偶者)
d.出生証明書等(永住者・特別永住者の実子)
e. 上記a~dのいずれかの書類等(定住者・家族滞在)
- 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明するいずれかの資料(定住者・家族滞在)
(1) 預貯金通帳の写し
(2) 不動産の登記事項証明書
- 住民税の課税(又は非課税)証明書
→直近3年分(日本人の配偶者)(永住者・特別永住者の配偶者)
→直近1年分(日本人の実子)(永住者・特別永住者の実子)
→直近5年分(定住者・家族滞在)
- 住民税の納税証明書
→直近3年分(日本人の配偶者)(永住者・特別永住者の配偶者)
→直近1年分(日本人の実子)(永住者・特別永住者の実子)
→直近5年分(定住者・家族滞在)
- 住民税を適正な時期に納めていることを証明する通帳の写し等(住民税が給与から天引きされていない方)
→直近3年分(日本人の配偶者)(永住者・特別永住者の配偶者)
→直近1年分(日本人の実子)(永住者・特別永住者の実子)
→直近5年分(定住者・家族滞在)
- ねんきん定期便又はネットの「各月の年金記録」の印刷画面
→直近2年分 (日本人の配偶者)(永住者・特別永住者の配偶者)(定住者・家族滞在)
→直近1年分(日本人の実子)(永住者・特別永住者の実子)
- 国民年金保険料領収証書の写し(直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方)
→直近2年分 (日本人の配偶者)(永住者・特別永住者の配偶者)(定住者・家族滞在)
→直近1年分(日本人の実子)(永住者・特別永住者の実子)
- 国民健康保険料納付証明書(国民健康保険に加入している方)
→直近2年分 (日本人の配偶者)(永住者・特別永住者の配偶者)(定住者・家族滞在)
→直近1年分(日本人の実子)(永住者・特別永住者の実子)
- 国民健康保険料領収証書の写し(国民健康保険に加入している方)
→直近2年分 (日本人の配偶者)(永住者・特別永住者の配偶者)(定住者・家族滞在)
→直近1年分(日本人の実子)(永住者・特別永住者の実子)
- 健康保険/厚生年金保険 料領収書の写し。または社会保険料納付証明書又は社会 保険料納入確認(申請)
→直近2年分 (日本人の配偶者)(永住者・特別永住者の配偶者)(定住者・家族滞在)
→直近1年分(日本人の実子)(永住者・特別永住者の実子)
- 親族一覧表(日本人の配偶者)(永住者・特別永住者の配偶者)(定住者・家族滞在)
⑤審査期間
永住許可申請の審査期間は、通常4か月から1年程度かかります。審査期間は申請内容や個別の状況により異なり、以下の要因が影響することがあります。
【審査期間に影響する要因】
- 提出書類の正確性と充実度:書類に不備がある場合や、追加資料の提出を求められた場合は審査が長引くことがあります。
- 申請者の経歴や状況:長期間にわたり安定した収入や納税が確認できる場合、比較的スムーズに審査が進む傾向があります。また在留歴に特記事項(例:オーバーステイや資格外活動の履歴など)がある場合、慎重な審査が行われる可能性があります。
- 入管の混雑状況:申請が集中する時期(年度末や新年度)や、入管の業務量によって審査期間が延びる場合があります。
- 家族全員で申請する場合:家族分の審査が必要なため、単身で申請する場合より時間がかかることがあります。
【審査状況の確認】
申請後、入管局で発行される「受付票」に記載された番号を使って、申請状況を確認することができます。ただし、具体的な進捗は入管から通知されないことが多いため、結果が出るまでは待つ必要があります。審査に時間がかかっている場合でも、通常は個別の問い合わせには応じてもらえないため、結果が届くのを待つことが一般的です。
不許可事例
⑥永住許可申請が不許可になる主な事例
以下のようなケースがあります。これらは、申請者の状況や入管の判断基準に基づいています。
【必要な条件を満たしていない場合】
- 在留期間の要件不足:通常、日本に10年以上継続して在留している必要があります(例外あり)。10年未満の場合、特例が適用される状況を満たしていないと不許可となります。特例として、日本人や永住者の配偶者、定住者などの場合、1年以上の婚姻や滞在歴が基準となります。
- 安定した収入や資産がない:生活基盤が不安定であると判断された場合、審査で不利になります。具体例としては、低所得や無職が続いている場合など。
- 納税義務を果たしていない:市民税や所得税、社会保険料の未納や滞納があると、不許可の原因となります。
【法律違反や社会的信用の問題】
- 過去に犯罪や違法行為を行った場合:交通違反(飲酒運転など)を含む法律違反があると、永住許可が難しくなります。特に、罰金刑や懲役刑の履歴がある場合は重大な影響があります。
- 資格外活動やオーバーステイの履歴:在留資格の範囲を超えた活動(無許可での労働など)や、過去に在留期限を超過して滞在していた場合。
【提出書類の不備や虚偽】
- 必要書類が不足している:指定された書類(住民票、納税証明書など)の提出が不完全な場合や、正確な内容でない場合。
- 虚偽の情報を申告した場合:申請書や添付資料に虚偽の内容が含まれていると、不許可になるだけでなく、将来の申請にも悪影響が及ぶ可能性があります。
【社会的信頼性の欠如】
- 頻繁な転職や退職:安定した職業に就いていない場合、経済的基盤が脆弱と判断される可能性があります。
- 家族の扶養状況に問題がある:扶養している家族が適切に生活できていない場合や、家族が社会保険に未加入である場合など。
【入管の判断による特別な理由】
- 在留資格に適合しない活動を行っている場合:例えば、「技術・人文知識・国際業務」の資格で単純労働を行っている場合など。
- 永住許可を得る必要性が低いと判断される場合:現在の在留資格で問題なく日本に滞在できると判断されると、永住許可が不要とされることがあります。
⑦不許可後の対応
不許可となった場合でも再申請は可能です。ただし、不許可理由をしっかり確認し、改善点を明確にしたうえで再度申請する必要があります。不許可理由は原則として入管で開示されるため、確認をおすすめします。
まとめ
「永住者」の在留資格は、日本国内で長期的に安定した生活を送る外国人に対して与えられるものであり、在留期間の制限がなく、職業や活動の自由度が高いというメリットがあります。一方で、自分でやる場合、多くの書類を適切に揃え申請することはとても大変です。また多くの書類は、時系列や理由など、すべての面で整合がとれていることを自分たちで確認しなければなりません。不許可の確率を可能な限り低減させるためにも入国管理局の審査に適した書類作成や手続きに精通した行政書士に相談/依頼することをお勧めします。
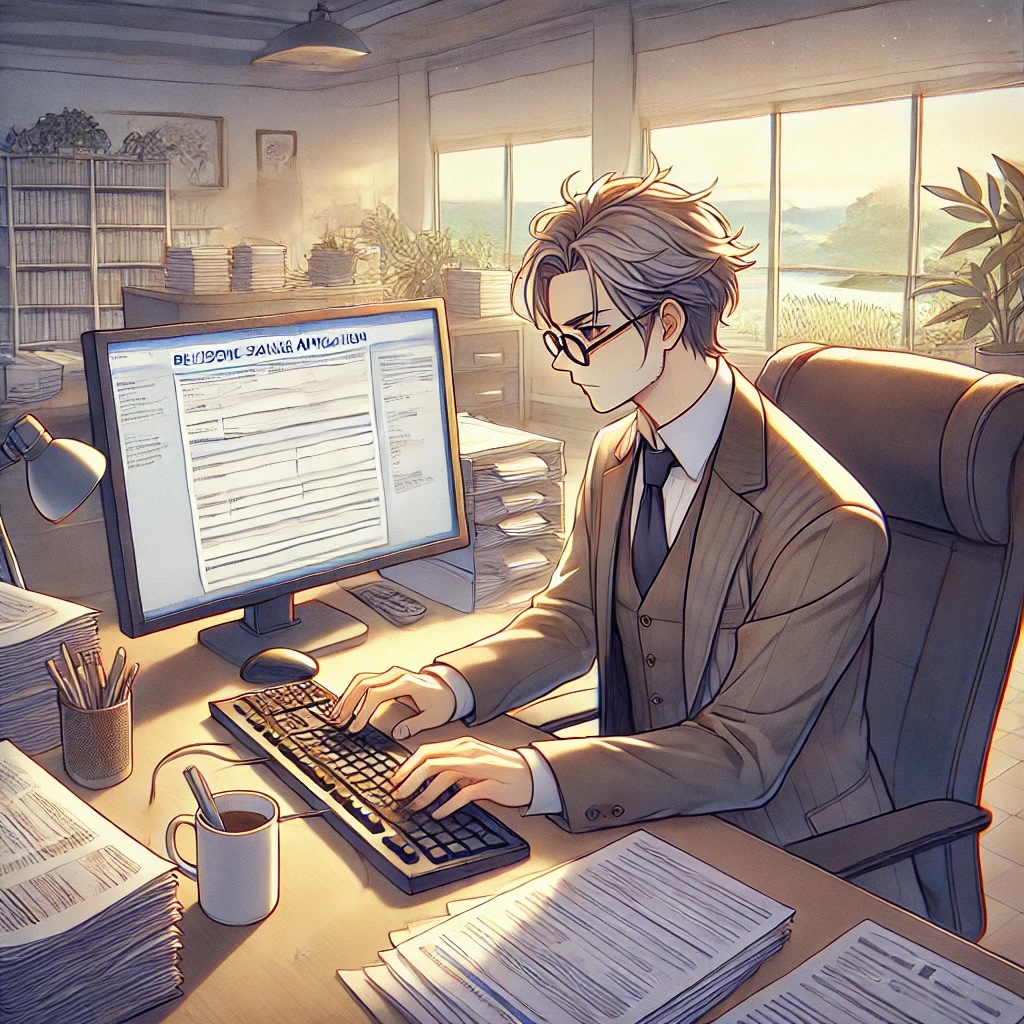
記事作成:浅野 長慈 (在留資格申請取次行政書士)
地方公共団体勤務の後、海外人材紹介会社、国内監理団体にて外国人材ビジネスを経験。2024年、アンコール事務所を開設。

